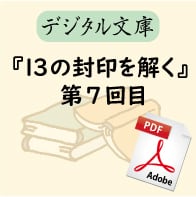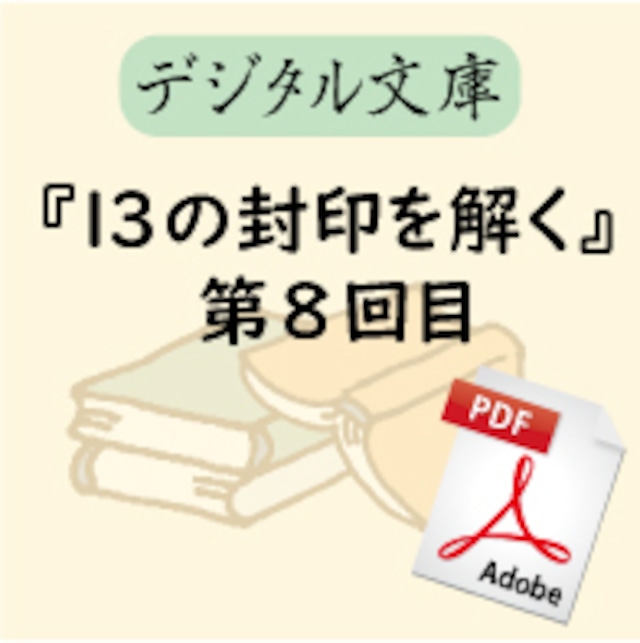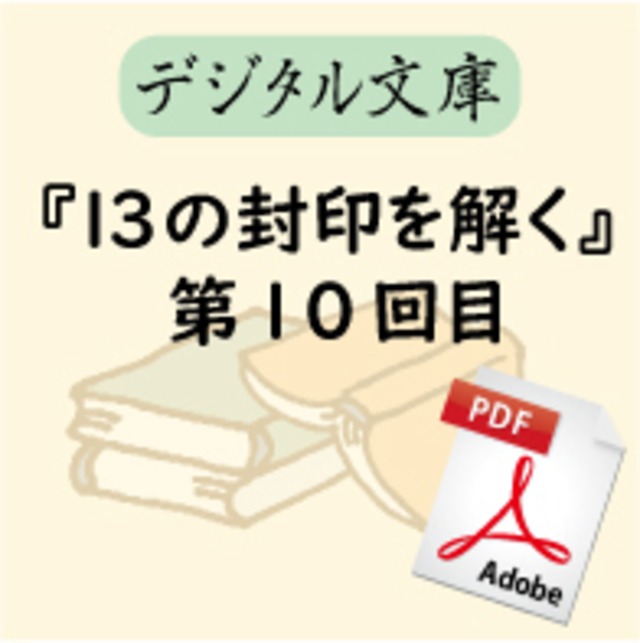Item
『13の封印を解く』 第7回目
(「13の封印を解く」第7回目.pdf)
13の封印を解く 第7回 ミクロの命数
後編です。
前編では 10のマイナス9乗 10乗の
塵(じん)→埃(あい) まで意識を静めて
きました。
次は、渺(びょう)→漠(ばく)→
模糊(もこ)→逡巡(しゅんじゅん)
→須臾(しゅゆ)→に進みます。
これらは、10のマイナス11乗→12乗
→13乗→14乗→15乗になります。
それでは、10のマイナス11乗の
渺(びょう)は、1000億分の1である
ことを示す漢字文化圏における数
の単位である。
埃 の1/10、漠 の10倍に当たる。
と、辞書にあります。
この漢字の意味は、果てしなく
広がる様子。または、ハッキリと見え
ない様子。 はるか。かすか。
はるか。果てしなく広がるさま
かすか。きわめて小さくはっきりと
見えないさま。
小さくて、よく見えないさま。
かすかなさま。また、遠すぎて、
はっきり見えないさま。
意味が矛盾していますが、
果てしなく遠すぎて、はっきり見えない、
という意味が多いようです。
使い方としては、:渺然(ビョウゼン)
・渺渺(ビョウビョウ) ・渺茫(ビョウボウ)
・渺漫(ビョウマン)
これらのすべてが『果てしなく広い』
の意味で使います。
あまり見慣れない漢字ですが・・・、
『天平の甍(いらか)』という歴史小説が
あり、その中で、渺漫(ビョウマン )という
言葉が使われています。
「日本へ行くには渺漫(びょうまん)
たる滄海(そうかい)を渡らねば
ならず、百に一度も辿たどりつか
ぬと聞いております。」
これは、鑑真和尚のお弟子さん
のセリフで、鑑真和尚が日本に行く
ことに反対して、述べた言葉です。
この中の渺漫(びょうまん)たる
滄海(そうかい)とは、果てしなく広い
日本海のことで、「中国から日本に
渡海することは難しく、百回に一度も
たどり着くことができない、と、
聞いております。」という意味になります。
これは、井上靖の奈良時代の
遣唐使として唐へ渡った名もなき
留学僧が、鑑真和上を来朝させる
という目的のために、命の危険を
冒してまで任務を遂行する歴史小説です。
西暦700年代、日本の若き僧侶
たちが遣唐使で中国の唐へ渡り
鑑真を日本へ召くための苦労が、
つまり、1300年前の遣唐使の留学僧
の艱難辛苦の史実が描かれている
物語で、感動的な小説です。
遣唐使の中には、運にも才能にも
恵まれ後世に名を残した最澄や
空海もいましたが、目的を果たせ
なくて日本に帰れなかった無名の
僧や学者のほうが圧倒的に多い
わけで、彼らの苦悩が痛切に感じ
られます。
ちなみに私の知人が井上靖の
熱狂的な読者で、同人雑誌まで発行
するほどでした。その人とは、よく
囲碁をしましたが、折に触れて井上靖
の小説の話もしてくれました。
井上靖氏がもう少しご存命だったら、
ノーベル文学賞は確実と思うくらい
素晴らしい文章を書く作家だと思います。
私も、中学3年の高校受験の時に、
受験勉強はほとんどせずに、日本
文学全集の81冊を、受験勉強だと
言って、読み込んでいました。
文学全集は、家の本棚にあったので、
難しい漢字や言葉は漢和辞典や百科
事典で調べながらの読書でしたから
家の人は、熱心に勉強していると
思ったことでしょう。
井上靖の『天平の甍(いらか)』は、
難しい漢字が多くて読むのに苦労
しましたが、内容は覚えていました。
大人になって再度読んだ時に、
渺の漢字に遭遇して辞書を引いたの
を覚えています。
話はそれていますが、鑑真和上
について、歴史の教科書からの
おさらいと、感想です。
今からおよそ1300年前、鑑真
和上は、正しい仏教を広めるため
日本にやってきました。
正しい仏教を伝えるため日本に
行くことを決めた鑑真でしたが、
渡航の許可が下りません。
そのため、無許可で日本に渡る
ことを決意します。
しかし、一度目は計画がもれて
失敗。二度目も、出港したものの
船が遭難して失敗します。
失敗を重ねて五度目、出港しま
したが、鑑真たちは嵐にあい、
漂流して日本とは反対の南の島
まで流されてしまいます。
鑑真は南方の気候や激しい
疲労などにより両眼を失明しました。
鑑真は六度目の挑戦でようやく
日本にたどりつきます。
日本をめざしてから十二年も
経っていました。
栄叡、普照ら留学僧たちは、
伝戒の師を求めて二十二年の旅をし、
その求めに応じた鑑真和上は、
五度の失敗と失明にも諦めず、
十二年後に日本の地を踏んだのです。
続きはダウンロードしてお楽しみ下さい。
後編です。
前編では 10のマイナス9乗 10乗の
塵(じん)→埃(あい) まで意識を静めて
きました。
次は、渺(びょう)→漠(ばく)→
模糊(もこ)→逡巡(しゅんじゅん)
→須臾(しゅゆ)→に進みます。
これらは、10のマイナス11乗→12乗
→13乗→14乗→15乗になります。
それでは、10のマイナス11乗の
渺(びょう)は、1000億分の1である
ことを示す漢字文化圏における数
の単位である。
埃 の1/10、漠 の10倍に当たる。
と、辞書にあります。
この漢字の意味は、果てしなく
広がる様子。または、ハッキリと見え
ない様子。 はるか。かすか。
はるか。果てしなく広がるさま
かすか。きわめて小さくはっきりと
見えないさま。
小さくて、よく見えないさま。
かすかなさま。また、遠すぎて、
はっきり見えないさま。
意味が矛盾していますが、
果てしなく遠すぎて、はっきり見えない、
という意味が多いようです。
使い方としては、:渺然(ビョウゼン)
・渺渺(ビョウビョウ) ・渺茫(ビョウボウ)
・渺漫(ビョウマン)
これらのすべてが『果てしなく広い』
の意味で使います。
あまり見慣れない漢字ですが・・・、
『天平の甍(いらか)』という歴史小説が
あり、その中で、渺漫(ビョウマン )という
言葉が使われています。
「日本へ行くには渺漫(びょうまん)
たる滄海(そうかい)を渡らねば
ならず、百に一度も辿たどりつか
ぬと聞いております。」
これは、鑑真和尚のお弟子さん
のセリフで、鑑真和尚が日本に行く
ことに反対して、述べた言葉です。
この中の渺漫(びょうまん)たる
滄海(そうかい)とは、果てしなく広い
日本海のことで、「中国から日本に
渡海することは難しく、百回に一度も
たどり着くことができない、と、
聞いております。」という意味になります。
これは、井上靖の奈良時代の
遣唐使として唐へ渡った名もなき
留学僧が、鑑真和上を来朝させる
という目的のために、命の危険を
冒してまで任務を遂行する歴史小説です。
西暦700年代、日本の若き僧侶
たちが遣唐使で中国の唐へ渡り
鑑真を日本へ召くための苦労が、
つまり、1300年前の遣唐使の留学僧
の艱難辛苦の史実が描かれている
物語で、感動的な小説です。
遣唐使の中には、運にも才能にも
恵まれ後世に名を残した最澄や
空海もいましたが、目的を果たせ
なくて日本に帰れなかった無名の
僧や学者のほうが圧倒的に多い
わけで、彼らの苦悩が痛切に感じ
られます。
ちなみに私の知人が井上靖の
熱狂的な読者で、同人雑誌まで発行
するほどでした。その人とは、よく
囲碁をしましたが、折に触れて井上靖
の小説の話もしてくれました。
井上靖氏がもう少しご存命だったら、
ノーベル文学賞は確実と思うくらい
素晴らしい文章を書く作家だと思います。
私も、中学3年の高校受験の時に、
受験勉強はほとんどせずに、日本
文学全集の81冊を、受験勉強だと
言って、読み込んでいました。
文学全集は、家の本棚にあったので、
難しい漢字や言葉は漢和辞典や百科
事典で調べながらの読書でしたから
家の人は、熱心に勉強していると
思ったことでしょう。
井上靖の『天平の甍(いらか)』は、
難しい漢字が多くて読むのに苦労
しましたが、内容は覚えていました。
大人になって再度読んだ時に、
渺の漢字に遭遇して辞書を引いたの
を覚えています。
話はそれていますが、鑑真和上
について、歴史の教科書からの
おさらいと、感想です。
今からおよそ1300年前、鑑真
和上は、正しい仏教を広めるため
日本にやってきました。
正しい仏教を伝えるため日本に
行くことを決めた鑑真でしたが、
渡航の許可が下りません。
そのため、無許可で日本に渡る
ことを決意します。
しかし、一度目は計画がもれて
失敗。二度目も、出港したものの
船が遭難して失敗します。
失敗を重ねて五度目、出港しま
したが、鑑真たちは嵐にあい、
漂流して日本とは反対の南の島
まで流されてしまいます。
鑑真は南方の気候や激しい
疲労などにより両眼を失明しました。
鑑真は六度目の挑戦でようやく
日本にたどりつきます。
日本をめざしてから十二年も
経っていました。
栄叡、普照ら留学僧たちは、
伝戒の師を求めて二十二年の旅をし、
その求めに応じた鑑真和上は、
五度の失敗と失明にも諦めず、
十二年後に日本の地を踏んだのです。
続きはダウンロードしてお楽しみ下さい。